Columm
古いホームページが信頼を失う5つのサイン
2025.8.14
ホームページ制作
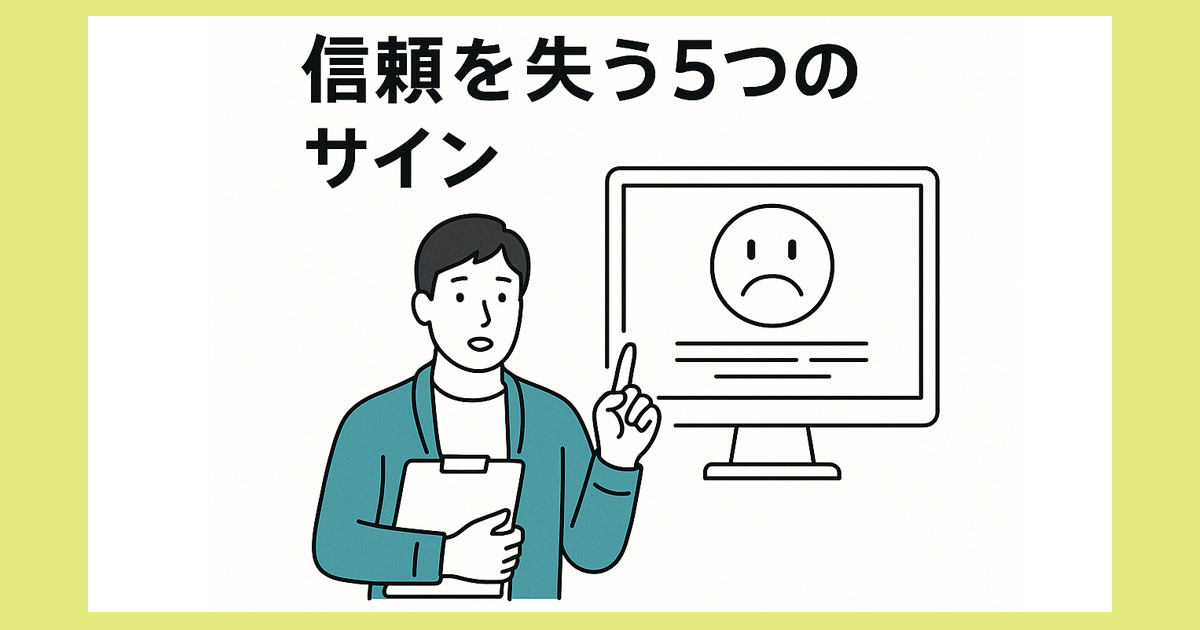
こんにちは、デザイナーの小林です!
日々お客様のホームページ制作やリニューアルに携わる中で、「もったいないな…」と思うサイトをよく見かけます。
そこで今回は「古いホームページが信頼を失う5つのサイン」をお伝えします。当てはまる項目があれば、それは改善のチャンスかもしれません。ぜひチェックしてみてくださいね。
目次
はじめに
ホームページは企業やお店の第一印象を決める「顔」です。
しかし開設から何年も経ち更新や改修をしないままでいると、デザインや機能が時代に合わなくなり、訪れた人に“古い”という印象を与えてしまいます。これは見た目の問題だけではなく、信頼や売上、採用、集客など、ビジネス全体に影響します。
「数年間まったく更新していない」「スマホで見ると見づらい」「写真が暗い」——こうした状態は、気づかないうちにお客様を遠ざけている可能性があります。
逆に言えば、これらを改善することで第一印象や成果は大きく変わります。
今回は古いホームページの危険信号と改善のヒントを5つのポイントに分けてご紹介します。
1. スマホ対応がされていない
現代のアクセスの大半はスマホ経由です。総務省の調査でもスマホ利用率は70%を超え、BtoBでもモバイル経由の閲覧が増加中です。
スマホ非対応サイトで起きやすい問題
- 文字が小さく読みにくい
- 横スクロールが必要
- ボタンやリンクが押しづらい
- レイアウト崩れで内容が正しく伝わらない
これらはすべて離脱の原因です。レスポンシブデザインを導入すれば、画面サイズに合わせて最適表示され、離脱率の低下・滞在時間の向上が見込めます。
スマホ非対応による離脱率は30〜50%増という事例もあります。
Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、スマホ表示が最適化されていないサイトは検索順位でも不利になります。
2. 情報が古いまま放置
情報の鮮度は信頼度と直結します。
「この会社、ちゃんと活動しているのかな?」と思われた時点で、問い合わせや来店の可能性は大きく下がってしまいます。
古さが目立つ例
- 数年前のイベント告知が残っている
- 退職したスタッフが紹介ページに掲載されている
- 閉店した店舗情報や古い電話番号が載っている
CMS(コンテンツ管理システム)を導入することで更新が簡単にできるようになります。ブログ感覚で更新でき、常に正しい情報を発信できます。また、ウェビーではお客様に代わり更新作業を行う「コンテンツ運用プラン」もあります。
BtoBでは企業概要・取引実績・採用情報の古さが特に悪影響を与えます。
検索エンジンは更新頻度を評価指標に含めるため、放置されたページはインデックス優先度が低下する可能性があります。例えば「更新ルール表」を作り更新担当・頻度・対象ページを明確化することで放置を防ぐことができます。

3. 画像や写真の解像度が低い
写真は言葉以上に印象を決めます。特に飲食・美容・観光・ECなど、ビジュアルが価値を左右する業種では致命的です。
悪印象を与える写真の例
- 暗くぼやけた商品写真
- 色味が不自然な画像
- 縦横比が崩れて引き伸ばされた写真
改善にはプロのカメラマンによる撮影や適切なレタッチ、Web用の最適化(画質維持+軽量化)が有効です。美しい写真は信頼を高め、コンバージョン率も向上します。
どうしても撮影が難しい場合には、有料のフリー素材を利用する方法もあります。
例)PIXTA、Aflo、iStock
推奨サイズは長辺1200px程度、JPEG圧縮率80%前後で画質と軽さを両立。スマホ閲覧が多い場合は縦構図写真を意識すると映えやすいです。また、背景色や余白をブランドカラーに合わせると、サイト全体の統一感が増します。
4. デザインが10年以上前のまま
デザイントレンドは年々変わります。古い配色や立体的なボタンは、現代では逆に「更新していないサイト」という印象を与えます。
古いデザインが与える影響
- 他社サイトと比較して見劣りする
- 検索結果でクリックされにくくなる
- ユーザーの滞在時間が短くなる
最新のWebデザインは、余白の活用、シンプルな配色、視線誘導の工夫が特徴です。デザイン刷新は見た目だけでなく、ブランド再構築の第一歩です。
古いデザインは可読性・操作性・視認性で不利になります。近年はカード型レイアウトやコンポーネント化などモジュール設計が主流で、運用や拡張性が向上しています。色覚特性やアクセシビリティ基準(WCAG 2.1など)に配慮すると利用者層を広げることができます。
5. 問い合わせ導線がわかりにくい
ホームページの目的は「見てもらうこと」ではなく、「行動してもらうこと」です。しかし、導線設計が不十分だと、興味を持ったユーザーでも離脱してしまう可能性があります。
導線設計で改善すべき点
- ボタンが目立たない色・位置になっている
- フォームの入力項目が多すぎる
- 問い合わせページが1クリックで辿り着けない
改善には、ページ上部・記事末尾・固定バナーなど複数箇所に問い合わせボタンを設置し、フォームは必要最低限に絞ることが効果的です。
ヒートマップ分析ツール(Microsoft Clarity、Hotjarなど)を利用すればユーザーがどこまでスクロールし、どこで離脱しているかが把握できます。入力フォームは1ページ1目的(問い合わせ、資料請求、予約などを分ける)にすると完了率が上がります。住所自動入力や入力候補表示などの補助機能は、完了率をさらに向上させます。
まとめ
今回ご紹介した5つのサインは、ユーザー体験と信頼性に直結します。1つでも当てはまったら、それはホームページを見直すタイミングです。
私たちは、現状診断からデザイン改善、写真撮影、運用サポートまで一貫して対応しています。まずは無料ホームページ診断で、改善の優先順位を一緒に整理しませんか?
見た目も成果も変わるホームページを一緒に作り上げましょう。

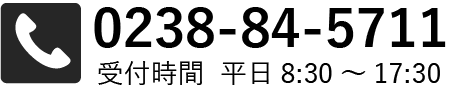
 無料相談・お問い合わせ
無料相談・お問い合わせ